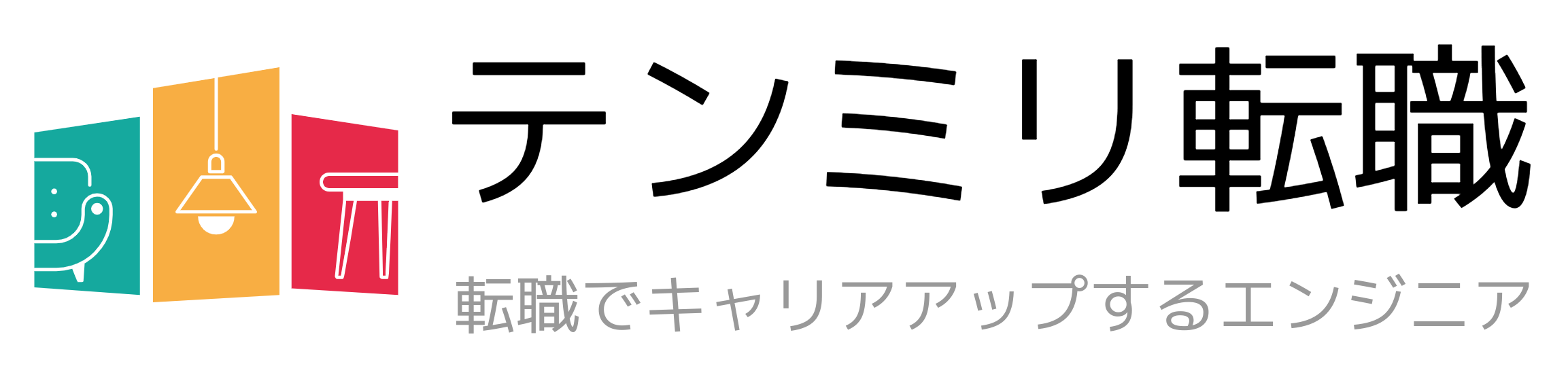はじめに
今日は、「はじめてのAWS(パート2)」という事で、Amazon Linux 2 について説明していきます。
ちなみに前回同様 Linux や その上での環境構築等の ある程度の経験があるエンジニアが初めて AWS を触る場合を想定しているので、AWS のこと以外は特に説明していません。その点はご了承ください。
前回の記事はこちら

Amazon Linux 2 とは
Amazon Linux 2 とは CentOS をベースに AWS がカスタマイズした Linux の事です。

パッケージ管理は CentOS で使われている yum ですが、リポジトリは AWS が管理しています。
/etc/yum.repos.d/amzn2-core.repo
ただし上記で管理しているのは基本的なパッケージのみなので、apache や php や mariadb 等が使いたい場合は amazon-linux-extras というコマンドで管理します。リポジトリは以下に記述されています。
/etc/yum.repos.d/amzn2-extras.repo

また、Amazon Linux 2 は 2023年6月30日までサポートが提供されます。※FAQより
Q:Amazon Linux 2 の長期サポートには何が含まれていますか?
Amazon Linux 2 の長期サポートは主要なパッケージにのみ適用され、以下の内容を含んでいます。
1) AWS では 2023 年 6 月 30 日まで、すべての主要なパッケージのセキュリティ更新とバグ修正を提供します。
2) AWS では、以下の主要なパッケージに対して、ユーザー空間のアプリケーションバイナリインターフェイス (ABI) の互換性を維持します。elfutils-libelf、glibc、glibc-utils、hesiod、krb5-libs、libgcc、libgomp、libstdc++、libtbb.so、libtbbmalloc.so、libtbbmalloc_proxy.so、libusb、libxml2、libxslt、pam、audit-libs、audit-libs-python、bzip2-libs、c-ares、clutter、cups-libs、cyrus-sasl-gssapi、cyrus-sasl-lib、cyrus-sasl-md5、dbus-glib、dbus-libs、elfutils-libs、expat、fuse-libs、glib2、gmp、gnutls、httpd、libICE、libSM、libX11、libXau、libXaw、libXext、libXft、libXi、libXinerama、libXpm、libXrandr、libXrender、libXt、libXtst、libacl、libaio、libatomic、libattr、libblkid、libcap-ng、libdb、libdb-cxx、libgudev1、libhugetlbfs、libnotify、libpfm、libsmbclient、libtalloc、libtdb、libtevent、libusb、libuuid、ncurses-libs、nss、nss-sysinit、numactl、openssl、p11-kit、papi、pcre、perl、perl-Digest-SHA、perl-Time-Piece、perl-libs、popt、python、python-libs、readline、realmd、ruby、scl-utils、sqlite、systemd-libs、systemtap、tcl、tcp_wrappers-libs、xz-libs、zlib
Amazon Linux 2 に LAMP ウェブサーバをインストールする
Amazon Linux 2 の amazon-linux-extras をつかって LAMP ウェブサーバを構築する例はこちらを参考にしてください。

amazon-linux-extras の分かりやすい説明はこちら

その他
セキュリティ脆弱性を修正するためのカーネルライブパッチの詳細を以下で公開しています。

AWS では各サービスの運用ステータスを以下で公開ています。

東京リージョンで何かあると、「Asia Pacific」のタブの一番上の「Recent Events」に表示されます。
まとめ
「はじめてのAWS(パート2)」という事で、Amazon Linux 2 について説明してみました。
このブログでは、こんな記事も書いてますので、よろしければ見ていってください。




それでは、また。